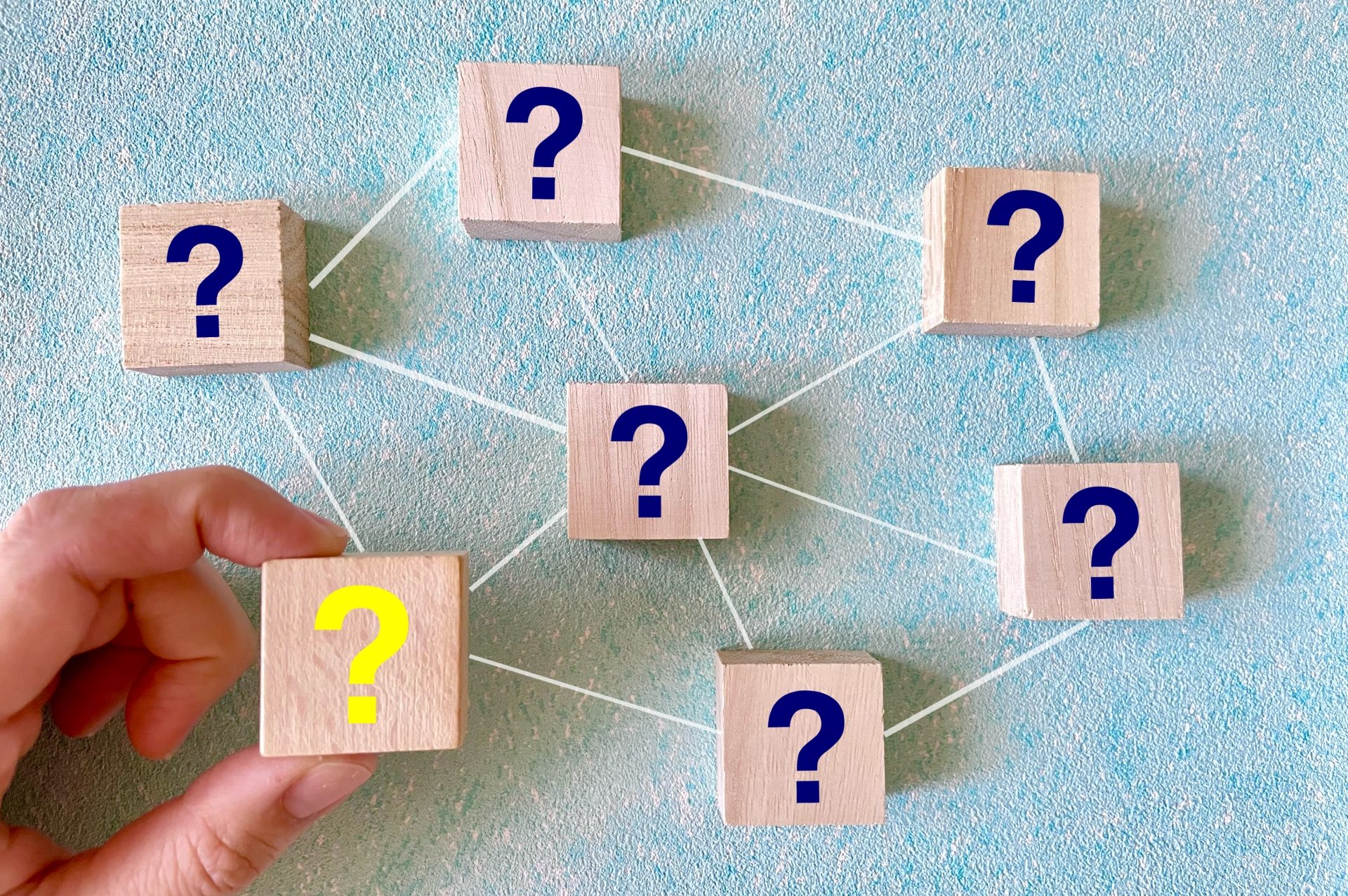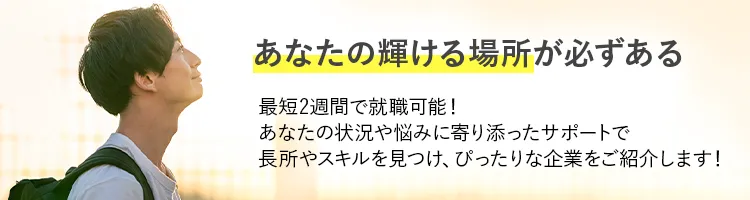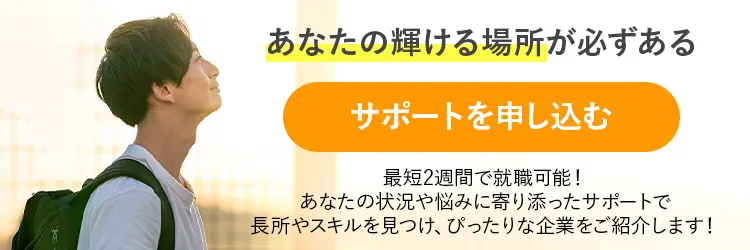[記事公開日]2025年8月8日
既卒とは?新卒・第二新卒との違いと就活のコツについて解説!
既卒とは、大学や専門学校などを卒業後に正社員として就職せず、現在も就職活動を続けている人を指します。
近年、既卒者の就職活動は新卒採用市場でも注目されており、多くの企業が既卒者を積極的に採用しています。
この記事では、既卒の定義から新卒・第二新卒との違い、就活を成功させるための具体的な方法まで、既卒者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
目次
既卒の基本定義と特徴
既卒とは、学校を卒業してから一度も正社員として就職していない人のことです。
既卒者の多くは、卒業後もアルバイトや派遣社員として働きながら就職活動を続けています。
既卒とは何かを詳しく解説
既卒の定義は、大学・短大・専門学校・高校などの教育機関を卒業した後、正社員として就職していない状態の人を指します。
卒業後の期間に明確な区切りはありませんが、一般的には卒業から3年以内の人を既卒と呼ぶことが多いです。
既卒者の背景は様々で、就職活動が思うようにいかなかった人のほか、公務員試験や資格取得に専念していた人、海外留学や語学学習に時間を充てていた人も含まれます。
また、内定を得ていたものの入社直前で辞退した場合も、既卒に該当するケースです。
厚生労働省の調査によれば、既卒者の就職率は年々改善傾向にあり、企業の受け入れ姿勢にも変化が見られ、既卒に対する理解が徐々に深まってきました。
実際、多くの企業が既卒者を「第二新卒」と同じように扱い、新卒採用の枠内で選考を行うことが一般的となっています。
既卒者の就職活動における立ち位置
既卒者は就職活動において、新卒と中途採用の中間的な立ち位置にあります。
新卒のようなフレッシュさを持ちながら、社会経験を積んだ実践的な視点も併せ持つ人材として評価されることが多いです。
企業側からみると、既卒者は新卒と同じように企業文化に馴染みやすく、一から育成できる人材として魅力的です。
同時に、アルバイトや派遣などの就労経験を通じて、基本的な社会人スキルを身につけている点も評価ポイントとなります。
採用市場では既卒者向けの求人が増加傾向にあり、「既卒・第二新卒歓迎」と掲げる企業も多くなっています。
これは企業が多様な人材を求めている現れであり、既卒者にとって就職のチャンスが広がっていると言えるでしょう。
既卒と新卒・第二新卒の違い
既卒と新卒・第二新卒の最も大きな違いは、就労経験の有無と卒業からの経過期間です。
それぞれの特徴を理解することで、自分に最適な就活戦略を立てることができます。
既卒と新卒の違いを徹底比較
新卒とは、大学や専門学校などを卒業見込みまたは卒業後1年以内で、正社員として就職したことがない人を指します。
一方、既卒は卒業後に正社員として就職していない人全般を指し、卒業からの期間に明確な制限はありません。
新卒の特徴:
- 卒業見込みまたは卒業後1年以内
- 就職活動のスケジュールが明確
- 同期入社の仲間がいる
- 企業の新卒研修制度を利用できる
既卒の特徴:
- 卒業後1年以上経過している場合が多い
- 就職活動のタイミングが自由
- アルバイトや派遣などの就労経験がある
- 社会人としての基礎スキルを身につけている
企業の採用活動において、新卒は一斉採用の対象となりますが、既卒は通年採用や中途採用の枠組みで応募することが多いです。
ただし、最近では既卒者も新卒採用の対象とする企業が増えており、選択肢の幅が広がっています。
既卒と第二新卒の違いとそれぞれの特徴
第二新卒とは、大学や専門学校を卒業後に一度就職したものの、短期間(一般的には3年以内)で退職し、転職活動を行っている人を指します。既卒との大きな違いは、正社員としての就労経験の有無です。
第二新卒の特徴:
- 正社員として就職経験がある
- 短期間で退職している
- 基本的なビジネスマナーを身につけている
- 転職理由を明確に説明する必要がある
既卒の特徴:
- 正社員としての就職経験がない
- アルバイトや派遣などの経験はある
- 新卒に近い扱いを受けることが多い
- 卒業後の期間の説明が求められる
企業の採用担当者は、第二新卒に対しては即戦力性を期待する一方、既卒に対しては新卒と同様の育成を前提とした採用を行うことが多いです。
既卒者は第二新卒と比べて、企業文化への適応性や成長ポテンシャルが重視される傾向があります。
企業が既卒者を採用する理由
企業が既卒者を採用する理由は多岐にわたりますが、主な要因は人材確保の必要性と、既卒者が持つ独特の価値にあります。
新卒採用だけでは十分な人材を確保しきれない企業にとって、既卒者は貴重な人材となっています。
彼らは新卒と同様の柔軟性を備えつつ、社会経験を通じて実践的なスキルを身につけている点が魅力です。
アルバイトや派遣での就労経験を通じ、基本的な社会人マナーやコミュニケーション能力を習得しているため、企業にとっては教育コストの削減にもつながります。
また、既卒者は就職に対する意欲が高く、企業への貢献意識が強いことが多いです。
卒業後も就職活動を継続している姿勢は、働く意欲の高さを示すものとして評価されています。
多くの企業が「第二新卒歓迎」という枠組みで既卒者を受け入れているのは、こうした価値を認めているからに他なりません。
既卒者が直面する就活の課題
既卒者の就職活動には、新卒とは異なる特有の課題があります。
これらの課題を理解し、適切に対策を講じることが就活成功の鍵となります。
既卒者特有の就活における困難
既卒者が就活で直面する最大の困難は、卒業後の空白期間に対する説明責任です。
面接時はほぼ必ず「なぜ卒業後すぐに就職しなかったのか」という質問がされます。この質問に対して納得のいく説明ができなければ、選考で不利になってしまうでしょう。
また、既卒者は新卒のような一斉採用の恩恵を受けにくく、求人情報の収集や企業とのマッチングに時間を要する点も課題といえます。
新卒向けの就職サイトや合同説明会の情報は豊富にある一方で、既卒者向けの情報は依然として限られているのが現状です。
加えて、同世代の多くがすでに就職しているため、孤独感や焦りを抱えやすくなります。
周囲からのサポートが得られにくく、モチベーションの維持に苦労することもあるでしょう。
企業の既卒者に対する先入観と対策
企業の採用担当者の中には、既卒者に対して「何か問題があるのではないか」という先入観を持つ人もいます。
「就活に失敗した人」「働く意欲が低い人」といったネガティブなイメージを持たれることがあります。
こうした先入観を払拭するためには、卒業後の期間を有効活用していることをアピールすることが必要です。
資格取得、語学学習、アルバイトでの経験など、成長につながる活動を行っていることを具体的に説明する必要があります。
また、既卒者は新卒よりも企業研究や業界研究に時間をかけることができるため、より深い理解を示すことで差別化を図ることができます。
企業の課題や将来性について具体的に言及し、自分がどのように貢献できるかを明確に示すことが重要です。
既卒者の心理的な不安要素
既卒者の多くが抱える心理的な不安として、「もう手遅れなのではないか」という気持ちがあります。
同期が社会人として活躍している姿を見ると、自分だけが取り残されたような感覚になることもあるでしょう。
また、面接での質問に対する不安は大きいものがあります。
「なぜ既卒になったのか」「この期間何をしていたのか」といった質問にどう答えればよいかわからず、就活の一歩を踏み出せない人も少なくありません。
こうした不安を克服するには、既卒者の成功事例を知ったり、同じ境遇の人とのネットワークを築いたりすることが効果的です。
さらに、既卒者向けの就活サポートサービスを利用すれば、専門的なアドバイスを受けることもできます。
既卒者の就活成功戦略
既卒者が就活を成功させるためには、自分の強みを明確にし、効果的なアピールが必要になります。
新卒とは異なるアプローチで、企業に価値を提供できる人材であることを示す意識が大事になってきます。
既卒者が就活で成功するための基本戦略
既卒者の就活成功の基本戦略は、「差別化」と「価値提供」の2つの軸で構成されます。
新卒との違いを明確にし、それを強みとして活用することが重要です。
まず、卒業後の期間を「空白期間」ではなく「成長期間」として捉え直すことが必要です。
アルバイトや派遣での経験、資格取得、語学学習など、この期間に得たスキルや知識を整理し、企業にとってのメリットとして提示します。
次に、企業研究を徹底的に行い、その企業が求める人材像を明確に把握します。
既卒者は新卒よりも時間的な余裕があるため、より深い企業研究が可能です。この強みを活かし、企業のニーズに合わせた自己PRを構築することが重要となります。
既卒者の強みを活かした自己PR方法
既卒者の強みは、新卒にはない「実践的な経験」と「成熟した判断力」です。
これらの強みを効果的にアピールするためには、具体的なエピソードと成果を交えた自己PRが必要です。
アルバイトや派遣での経験では、単に「接客をしていました」ではなく、「売上向上のために顧客のニーズを分析し、提案営業を行った結果、月間売上が20%向上しました」といった具体的な成果を示しましょう。
また、既卒者は就職に対する意欲が高いことも強みの1つです。
「なぜこの企業を選んだのか」「どのような貢献をしたいのか」について、新卒よりも深く考えられることをアピールしましょう。
既卒者向けの効果的な企業選び
既卒者の企業選びにおいては、「既卒歓迎」を明確に掲げる企業を優先することが重要です。
こうした企業は既卒者の価値を正しく評価しており、選考過程においても公平な判断が下されることが期待できます。
また、成長著しい企業や人手不足が深刻な業界では、既卒者のニーズが高く、特にIT業界、介護業界、営業職などで積極的な採用が見受けられます。
企業規模についても配慮が必要であり、大手企業は新卒採用に注力する傾向が強いものの、中小企業やベンチャー企業は既卒者の採用に対し柔軟に対応している場合が多いです。
以上を踏まえ、自己の希望と企業のニーズを的確にマッチングさせることが、就職活動成功の鍵となるでしょう。
既卒者の求人探しと応募のコツ
既卒者の求人探しには、新卒とは異なるアプローチが必要です。
効率的な求人情報の収集方法と、応募時の注意点を理解することで、就活の成功率を高めることができます。
既卒者向けの求人情報収集方法
既卒者向けの求人情報は、複数のチャネルを組み合わせて収集することが重要です。
一般的な求人サイトだけでなく、既卒者専門の就職サイトや転職エージェントも活用しましょう。
主要な求人情報源:
- 既卒者向け就職サイト(マイナビ既卒者向け、リクナビ既卒者向けなど)
- 転職サイト(中途採用枠での応募)
- 転職エージェント(キャリアアドバイザーのサポート)
- 企業の公式サイト(採用情報の直接確認)
- ハローワーク(公的機関の求人情報)
特に転職エージェントの活用は、既卒者にとって大きなメリットがあります。
専門のキャリアアドバイザーが、既卒者の状況を理解した上で適切な求人を紹介してくれるため、効率的な就活が可能となるでしょう。
応募書類作成のポイント
既卒者の応募書類では、卒業後の期間について明確に説明することが重要です。
履歴書の学歴・職歴欄では、卒業後の活動を時系列で整理し、空白期間を作らないよう注意します。
履歴書作成のポイント:
- 卒業後の活動(アルバイト、資格取得、語学学習など)を詳細に記載
- 志望動機では、なぜその企業を選んだのかを具体的に説明
- 自己PRでは、卒業後の経験から得たスキルを強調
- 写真は清潔感のある服装で撮影
職務経歴書については、アルバイトや派遣での経験も含めて作成します。
単なる業務内容の列挙ではなく、どのような成果を上げたのか、どのようなスキルを身につけたのかを具体的に記載することが重要です。
面接対策と注意点
既卒者の面接では「なぜ既卒になったのか」という質問は避けて通れません。
この質問に対する回答を事前に準備し、ポジティブな印象を与えるよう心がけます。
面接対策のポイント:
- 既卒になった理由を正直に、かつ前向きに説明
- 卒業後の期間で得た経験やスキルを具体的にアピール
- 企業への志望動機を明確に伝える
- 将来のキャリアプランを具体的に示す
面接では、既卒者であることをハンディキャップと捉えず、むしろ多様な経験を積んだ人材としてアピールすることが重要です。
新卒とは異なる視点や経験を持っていることを強みとして活用します。
既卒者が避けるべき就活の注意点
既卒者の就活では、特有の落とし穴があります。
これらの注意点を理解し、適切に対策を講じることで、就活での失敗を防ぐことができます。
既卒者がやってはいけない就活NG行動
既卒者の就活で最も避けるべきNG行動は、卒業後の期間について嘘をついたり、曖昧な説明をしたりすることです。
面接官は経験豊富であり、不誠実な回答はすぐに見抜かれてしまいます。
主なNG行動:
- 卒業後の期間について嘘をつく
- 空白期間を作らないために無理な理由をでっち上げる
- 新卒と同じような就活スタイルを続ける
- 既卒であることを隠そうとする
- 面接で言い訳ばかりする
特に、既卒になった理由について言い訳がましい説明をすると、かえって逆効果となります。
企業が知りたいのは、その期間に何を学び、どのように成長したかという点です。
素直に現状を認め、前向きな姿勢を示すことが大切となってきます。
応募企業選びでの失敗パターン
既卒者の企業選びでよくある失敗パターンは、「とにかく内定をもらいたい」という焦りから、自分に合わない企業に応募してしまうことです。
これは結果的に早期退職につながる可能性があります。
企業選びの失敗パターン:
- 既卒不可の企業に応募し続ける
- 企業研究を怠り、ミスマッチを起こす
- 条件面だけで企業を選ぶ
- 成長性のない業界や企業を選ぶ
- 自分のスキルや経験と全く関係のない業界を選ぶ
既卒者は新卒よりも転職のリスクが高いため、長期的に働ける企業を選ぶことが重要です。
短期的な内定獲得を目標にするのではなく、キャリア形成の観点から企業を選択していきましょう。
面接での回答で気をつけるべき点
既卒者の面接では、質問に対する回答の仕方が合否に大きく影響します。
特に、既卒になった理由や卒業後の活動について説明する際は、慎重に回答する必要があるでしょう。
面接回答の注意点:
- ネガティブな理由だけでなく、そこから学んだことを必ず含める
- 具体的な事例や数字を交えて説明する
- 将来に向けた前向きな姿勢を示す
- 企業への貢献意欲を明確に伝える
- 短期的な目標だけでなく、長期的なキャリアプランも示す
面接では、既卒者であることを弱みとして捉えるのではなく、多様な経験を積んだ人材としてアピールすることが重要です。
新卒とは異なる価値を提供できることを明確に示します。
既卒とフリーター・転職の関係性
既卒者の中には、フリーターとして働いている人や、将来的に転職を考えている人も多くいます。
それぞれの関係性を理解し、適切なキャリア戦略を立てることが重要です。
既卒とフリーターの違いと共通点
既卒とフリーターは重複する部分もありますが、定義や社会的な位置づけに違いがあります。
既卒は学歴に基づく分類であり、フリーターは就労形態に基づく分類です。
既卒とフリーターの共通点:
- 正社員として就職していない
- アルバイトや派遣で生計を立てている
- 就職活動を行っている(場合が多い)
- 企業からの評価が類似している
既卒とフリーターの違い:
- 既卒は学歴が明確(大学・専門学校等の卒業者)
- フリーターは年齢層が幅広い(学歴不問)
- 既卒は卒業後の期間が重要な要素
- フリーターは就労形態が重要な要素
既卒者の多くがフリーターとして働いているため、就活では両方の側面を考慮した戦略が必要です。
フリーターとしての経験を前向きに評価し、正社員になるための明確な動機を示すことが重要です。
既卒者の転職活動における位置づけ
既卒者は正社員経験がないため、厳密には「転職」ではなく「就職」活動を行っています。
しかし、転職サイトや転職エージェントを活用することも多く、転職市場での位置づけを理解することが重要です。
転職市場において、既卒者は「未経験者」として扱われることが多いです。これは新卒と似た扱いを受けることを意味し、ポテンシャル採用の対象となります。
一方で、年齢が上がるにつれて、即戦力性を求められる傾向も強くなります。
既卒者が転職活動を行う際は、自分の年齢と経験を考慮し、適切な市場を選択することが重要です。
20代前半であれば新卒に近い扱いを受けますが、20代後半になると高確率で即戦力性を求められるでしょう。
既卒から正社員への道筋
既卒から正社員になるための道筋は複数あります。
最も一般的なのは、既卒者向けの新卒採用枠での応募ですが、その他にも様々な方法があります。
正社員への主な道筋:
- 既卒者向け新卒採用での応募
- 中途採用(未経験者歓迎)での応募
- 派遣社員から正社員への転換
- アルバイトから正社員への登用
- 職業訓練を受けてからの就職
それぞれの道筋にはメリット・デメリットがあります。
既卒者向け新卒採用は競争が激しいですが、新卒と同様の研修制度を利用できます。
中途採用は即戦力性を求められますが、選択肢が多いです。
重要なのは、自分の状況や希望に合った道筋を選択することです。
短期的な就職を優先するのか、長期的なキャリア形成を重視するのかによって、最適な選択肢は変わってきます。
既卒者向けの就職活動対策とコツ
既卒者が就職活動を成功させるためには、効果的な対策とコツを知っておくことが重要です。
新卒とは異なるアプローチで、自分の強みを最大限に活かす戦略を立てましょう。
既卒者の就活スケジュール管理
既卒者の就活では、新卒のような決まったスケジュールがないため、自分でペースを管理する必要があります。
計画的に活動を進めることで、効率的な就活が可能になります。
効果的なスケジュール管理のポイント:
- 週単位での目標設定(応募数、面接数など)
- 月単位での進捗確認と軌道修正
- 企業研究や自己分析の時間確保
- 面接対策やスキルアップの時間配分
- 精神的なリフレッシュの時間も確保
既卒者は時間的な制約が少ない分、だらだらと就活を続けてしまうリスクがあります。
明確な目標とスケジュールを設定し、集中的に取り組むことが成功の鍵となります。
業界・職種選びのコツ
既卒者の業界・職種選びでは、自分の経験やスキルを活かせる分野を選ぶことが重要です。
同時に、将来性や成長性も考慮した選択が必要です。
業界選びのポイント:
- 既卒者の採用に積極的な業界を選ぶ
- 成長性の高い業界を優先する
- 自分のアルバイト・派遣経験を活かせる業界を検討
- 人手不足の業界では採用の可能性が高い
- 未経験者歓迎の求人が多い業界を狙う
職種選びでは、営業職、事務職、サービス業など、未経験者でも始めやすい職種から検討することをおすすめします。
専門性の高い職種を希望する場合は、資格取得や職業訓練を活用することも有効です。
面接での差別化ポイント
既卒者が面接で差別化を図るためには、新卒にはない独自の価値を明確に示すことが重要です。
経験の豊富さと成熟した判断力をアピールポイントとして活用します。
面接での差別化ポイント:
- 実践的な経験に基づく具体的なエピソード
- 困難を乗り越えた経験とそこから学んだこと
- 多様な職場での経験から得た適応力
- 明確な目標意識と企業への貢献意欲
- 長期的なキャリアプランの提示
面接では、既卒者であることを弱みとして捉えるのではなく、多様な経験を積んだ人材としてアピールすることが重要です。
新卒とは異なる価値を提供できることを明確に示しましょう。
既卒者が活用すべき就活サポート
既卒者の就活では、様々なサポートサービスを活用することで、効率的に活動を進めることができます。
適切なサポートを受けることで、就活の成功率を高められるでしょう。
就職エージェントの活用方法
就職エージェントは、既卒者の就活において非常に有効なサポートツールです。専門のキャリアアドバイザーが、個々の状況に応じた適切なアドバイスと求人紹介を行ってくれます。
就職エージェントのメリット:
- 非公開求人へのアクセス
- 専門的なキャリアアドバイス
- 面接対策や書類添削のサポート
- 企業との条件交渉の代行
- 就活全般の相談相手
既卒者向けの就職エージェントでは、既卒者の特徴を理解したアドバイザーが対応するため、より適切なサポートを受けることができます。
複数のエージェントに登録し、比較検討することをお勧めします。
ハローワークでの支援制度
ハローワークでは、既卒者向けの様々な支援制度を提供しています。
公的機関ならではの幅広いサービスを無料で利用できるため、積極的に活用しましょう。
ハローワークの主な支援制度:
- 職業相談・職業紹介
- 職業訓練の案内
- 履歴書・職務経歴書の作成支援
- 面接対策セミナー
- 就職支援セミナー
特に、「わかものハローワーク」では、既卒者を含む若年者向けの専門的なサポートを受けることができます。
キャリアカウンセリングや就職支援セミナーなど、充実したサービスが提供されています。
既卒者向けの就職フェアやイベント
既卒者向けの就職フェアやイベントでは、既卒者の採用に積極的な企業と直接話をすることができます。
効率的な情報収集と企業とのマッチングが可能です。
就職フェア・イベントのメリット:
- 多数の企業と一度に接触できる
- 企業の人事担当者と直接話ができる
- 既卒者向けの求人情報を効率的に収集できる
- 他の既卒者との情報交換ができる
- 就活のモチベーション向上につながる
就職フェアでは、事前に参加企業の情報を調べ、興味のある企業を絞り込んでから参加することが重要です。
また、企業の担当者との会話では、単なる情報収集だけでなく、自分のアピールも忘れずに行いましょう。
まとめ
既卒とは、卒業後に正社員として就職していない人を指し、現在では貴重な人材として注目されています。
既卒者は、新卒にはない経験や柔軟性を活かし、戦略次第で十分に就職を成功させることが可能です。
卒業後の期間を成長の時間と捉え、得たスキルや経験を積極的にアピールする姿勢が重要になってくるでしょう。
「なぜ既卒になったのか」への前向きな説明や明確な将来ビジョンを示すことは、企業に好印象を与えるポイントになります。
また、既卒者向けの求人や就職フェア、就職支援サービスの活用も効果的です。
大切なのは、自分の状況を正しく理解し、それを強みに変える視点。焦らず着実に準備を進め、自信を持って臨むことが、成功への近道となるでしょう。
ジールコミュニケーションズでは、新卒・既卒での就職活動、第二新卒、中途で転職活動をはじめ、企業向けの採用支援や学校・キャリアセンター向けのサポート支援を行っております。豊富な実績や手厚いサポートによってお客様に向き合った支援サービスをご提供いたします。
お問い合わせよりお気軽にお悩みや希望をご相談ください。
問い合わせから相談する