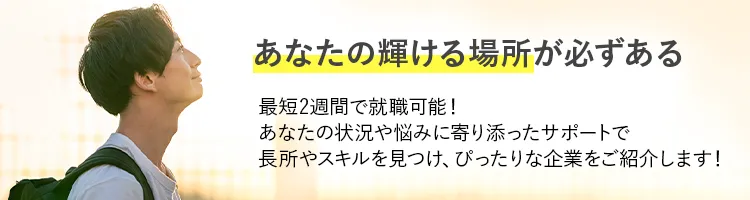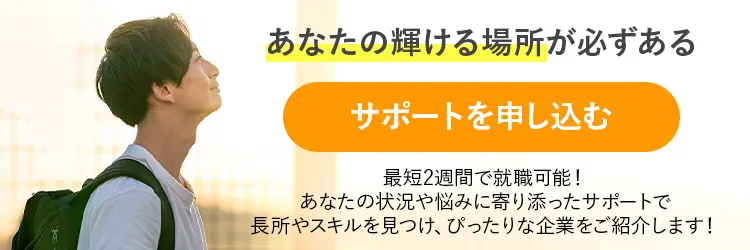[最終更新日]2023年9月29日 [記事公開日]2021年7月27日
第二新卒と既卒との違いとは?どこよりもわかりやすく違いを解説します
第二新卒と既卒。似ているようで違うこの2つの意味を知っていますか?新卒じゃない今、転職を行ううえではこの2つの意味をしっかりと理解しておかなくてはなりません。
自分がどちらの立場で就活をしていくのか、またそれぞれの就職の難しさとはいったい?
今回このコラムではそんな第二新卒既卒との違いをプロがどこよりもわかりやすく解説していきます。それぞれの意味と違いはもちろん、それぞれの対策法や受かるためのやり方について解説していますので、ぜひ最後までご覧ください!
第二新卒と既卒の違い
転職活動をしていると、「第二新卒」や「既卒」という言葉を目にすることがあります。実はこの2つの言葉、就活市場では全く異なる意味を持っているのです。まず、「第二新卒」という言葉には法的な定義はありません。しかし、第二新卒とは一般的に、学校を卒業してから約3年以内に一度就職した人を指します。学校には短大、専門学校、高校の卒業生も含まれます。ただし、企業によっては大卒者しか受け付けないところもありますので、募集要項をよく確認してください。
では、既卒の場合はどうでしょうか?新卒同様、既卒という言葉にも明確な定義はありませんが、一般的には学校を卒業したものの、正社員として働いた経験のない人を指します。厚生労働省では就職して3年未満の既卒者を採用した場合に奨励金を支給していますので、就職して3年未満の人を既卒者と呼ぶことが多いようです。また、卒業後3年以内であれば、新卒者として応募できる場合もあります。当然のことですが、学校を卒業したからといって、すぐに新卒採用の対象から外れるわけではありません。
第二新卒で行う転職の実情と対策法
では、第二新卒の転職事情はどうなっているのでしょうか。厚生労働省の2019年10月の発表によると、大学新卒者の3年以内の離職率は32.0%で、前年よりも0.2ポイント高くなっています。過去の傾向を見ると、大学新卒者の就職後3年以内の離職率は、おおむね30%台前半で推移しています。この数字が示すように、新卒者の約3人に1人が3年以内に転職していることになります。事業規模別に見ると、従業員5人未満の企業では57.7%、5人以上29人未満の企業では49.7%が離職しており、事業規模が大きいほど離職者数が減少する特徴が見られます。
企業側の採用事情も確認しておきましょう。近年、人材紹介業界では第二新卒者の需要が高まっています。その背景には、新卒者の就職市場が売り手市場になっていることがあります。つまり、求人数に対して学生の数が少ないため、企業は思うように新卒者を採用できないのです。また、前述したように、新卒者の3人に1人は3年以内に会社を辞めてしまう現実があります。そのため、若い人材を確保する手段として、第二新卒が今、注目されているのです。これは第二新卒社にとって朗報と言えるのではないでしょうか。
第二新卒で就職活動をする際、どのような資質が求められるか、転職に受かるためにも、必ず以下のポイントを押さえておきましょう。企業が最も第二新卒者に求めているのは、責任感、意欲、そして仕事への熱意です。企業側は、第二新卒者が「途中で仕事を辞めてしまうのではないか」「働く意欲がないのではないか」「どこでもいいから就職したいのではないか」と懸念しています。そのため、応募者が責任感を持って仕事に取り組んでくれると安心させることが大切です。その際、前職での具体的なエピソードを交えてアピールすると効果的です。
第二新卒者は、新卒者よりも社会人としての経験を積んでいるため、より「即戦力」であると考えられます。スキルや実績がまだ浅いのは仕方ありませんが、社会人としてのマナーやメールの書き方、名刺交換の仕方など、最低限のビジネススキルは身についているものと思われます。
また、企業は第二新卒者にコミュニケーション能力を求めています。新卒者と違って、企業や組織で即戦力として働くことを期待しているので、社内外の様々な人と問題なく接することができるかどうかは大きなポイントとなります。ここでいうコミュニケーションとは、単に会話が成立することだけではありません。社会人としてのコミュニケーションとは、相手の意図を理解し、相手の立場に立って言葉を選び、伝えることができる能力のことです。集団の中で自分の立場や相手の立場を理解し、痒いところに手が届くような言動ができれば、思いやりのある人、コミュニケーション能力の高い人と評価されるでしょう。
採用担当者だけでなく、配属先の部署の上司や他のスタッフからも面接を受ける場合、「部署の人がこの人と一緒に働きたいと思うか」という視点で見られることもあります。たとえスキルや経験が少なくても、「この人と一緒に働きたい」と思わせるような人柄や熱意をアピールすることで、最終選考に残る可能性を高めることができます。
第二新卒の場合、応募する前に、できるだけ仕事について理解しておく必要があります。社会人経験が多少なりともある訳ですから、ある程度は業務内容を把握した上で応募しているだろうと相手も考えます。応募を考えている会社の仕事内容を自分で調べたり、転職エージェントを利用したりして、「その部署がどんな仕事をしていて、自分はどう貢献したいのか」を理解しておくようにしましょう。
既卒で行う就職の実情と対策法
現実には、新卒者よりも既卒者の方が就職活動が難しいと言われています。事実、新卒者の大半が内定を得ているのに対し、既卒者は約半数しか内定を得られないということがあります。新卒の方が就職活動で有利なのは単純に募集枠が多いという理由が大きいですが、企業にとっても、優秀な若手を多く採用できたり、同期入社の人材を一度に育成できたりと、さまざまなメリットがあります。特に、大手企業では新卒者を大量に採用する傾向があるので、既卒者は不利になりがちです。
また、中途採用では即戦力が求められるため、仕事の経験を積んでいる人が有利になります。社会人経験の少ない既卒者は、中途採用では不利になるのが現実です。採用担当者の中には、既卒者に対して「新卒での就職活動がうまくいかなかったのではないか」「正社員として就職できなかった理由があるのではないか」というマイナスイメージを持っている人もいるでしょう。このネガティブなイメージを払拭するためには、「なぜこの会社で働きたいのか」「どんなスキルが使えるのか」「何を目指しているのか」を具体的に述べて、自分の将来像を明確にし、企業側の不安を払拭できるように準備しておくことが大切です。
とはいえ、少子高齢化で若者が不足しているため、既卒者を採用したいと考える企業が増えています。また、期待していた数の新卒者を採用できなかった企業が、既卒者を採用するケースもあります。さらに、新卒者の応募は大企業が中心となる傾向があるため、中小企業を中心に既卒者の需要が高まっています。就活では不利になりがちな既卒者ですが、既卒者の需要は高まっていますので、あきらめずに頑張ってください。
既卒者の就活における強みとは一体何でしょうか。新卒者は入社日が決まっていて1年以上待たされることもあるのに対し、既卒者はすぐに仕事を始めることができます。そのため、人手不足で早く仕事を覚えてほしいと考えている企業は、新卒よりも既卒を積極的に採用します。また、新卒で正社員として就職できなかった経験を乗り越えて、就職活動をしている既卒者の可能性を評価する企業もあります。
既卒者は社会人経験がないため、逆に応募先の企業の働き方に柔軟に対応できる点も強みとなるでしょう。転職者の場合、自分のやり方があり、新しい環境に適応するのは難しいかもしれません。その点、既卒者は一から教育しやすいので、時間をかけてスタッフを育てたいと考えている雇用主には需要があります。
既卒者の場合、就職活動を成功させるためには、履歴書の書き方や企業研究を入念に行うなどの準備が必要です。時期によって求人数は変動しますが、いつ応募したい仕事が見つかるかわかりません。時期を問わず、いつでも就職活動を始められるように準備しておくことが大切です。既卒の就職活動は、できるだけ早く始めることをお勧めします。就活は一年中応募することになりますので、いつ始めるかにこだわる必要はありません。仕事を見つけたいと思ったときに始めましょう。
先に述べたように、既卒者は就職活動において不利な立場にありますが、10代、20代には性格ややる気を重視した潜在的な仕事が多いので、チャンスはたくさんあります。もう卒業したから正社員になれないと思っていると、手遅れになってしまいます。できるだけ多くの企業情報を集め、積極的に応募すれば、就職の可能性は高まるでしょう。
求人は1年中募集していますが、新年度が始まる前の3月と、夏のボーナスが終わった後の10月は、離職者が増えるため、求人数が増える傾向にあります。これらの時期に備えて準備をしておくとよいでしょう。
既卒が就活を成功させるためには、自己分析をして、企業にアピールできる自分の強みを見つけることも大切です。自己分析は新卒者に限らず、就職活動に必要な準備です。自分の長所、短所、価値観を考え、これまでの経験で頑張ったこと、達成したことを振り返ってまとめてみましょう。自己分析が苦手な方は、身近な人にお願いして「他己分析」をしてもらう方法もあります。
「やりたいことがわからない」「応募する会社が見つからない」という方には、世の中にある職種や業界について調べてみることをおすすめします。自分の興味や趣味を活かした仕事を探してみると、やりたいことが見つかるかもしれません。新卒であれば大学の就職関連のイベントや相談窓口が充実しているので、知らなかった企業や仕事に出会う機会もありますが、既卒は自分で情報を集めないと、視野がなかなか広がりません。就活サイトや人材紹介会社などを利用して、幅広く情報を集め、自分に合った企業を見つけましょう。
既卒者は、履歴書や職務経歴書を書くときに、新卒以上に工夫が必要です。既卒者は実務経験がないので、アルバイトでの経験や実績をアピールしたり、入社後に活かせる強みを挙げたりと、採用するメリットが伝わるような書き方をすることが大切です。履歴書や職務経歴書は、第三者にチェックしてもらうのがよいでしょう。そうすれば、自分では気づかないような誤字・脱字にも気づくことができます。家族や友人に履歴書をチェックしてもらうのも良いですが、プロの就職エージェントを利用するのも良いでしょう。特に、初めての就活で書き方が分からないという方にはお勧めです。
求人情報の中で「既卒者歓迎」と書かれている求人を中心に就活をするのも、受かりやすい方法です。既卒者は新卒採用や中途採用にも応募できますが、選考で不利になることがあります。その点、企業が「既卒者歓迎」と募集しているのであれば、既卒者の採用に熱心であることを意味し、採用される可能性が高くなります。企業が「既卒者歓迎」と求人広告を出す理由は、若い人が足りないとか、新しい事業を立ち上げるなど、さまざまです。
第二新卒と既卒どっちが成功しやすいのか?
第二新卒者と既卒者のどちらが成功しやすいかは、企業の考え方や採用条件にもよるので、一概には言えません。一般的には、新卒者と第二新卒者がまったく同じ仕事に応募した場合、第二新卒者の方が有利になります。なぜなら、働いたことのない人を一から育てるのは非常に難しいからです。ある程度の社会的マナーを身につけた人材を採用することで、企業は新入社員の教育にできるだけ時間をかけず、即戦力になって欲しいと考える企業が多いです。
離職経験のある第二新卒者の場合、当然ながら「すぐに辞めてしまうのではないか」という懸念もあります。ただ、新卒や既卒だからといって離職率が低いわけではなく、すでに一度採用されている第二新卒としては、やはり若干有利になります。しかし、先に述べたように、既卒者と第二新卒者にはそれぞれメリットとデメリットがあります。採用面での両者の違いはごくわずかで、会社や担当者によっても異なります。
まとめ
第二新卒と既卒の違いは、学校を卒業してから3年以内に働いたことがあるかないかだけです。それぞれメリット・デメリットは異なりますが、実際の就職活動においては大きな違いはありません。それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、第二新卒・既卒の今しかできないアピールポイントを使って就活を始めましょう。
ジールコミュニケーションズでは、新卒・既卒での就職活動、第二新卒、中途で転職活動をはじめ、企業向けの採用支援や学校・キャリアセンター向けのサポート支援を行っております。豊富な実績や手厚いサポートによってお客様に向き合った支援サービスをご提供いたします。
お問い合わせよりお気軽にお悩みや希望をご相談ください。
問い合わせから相談する